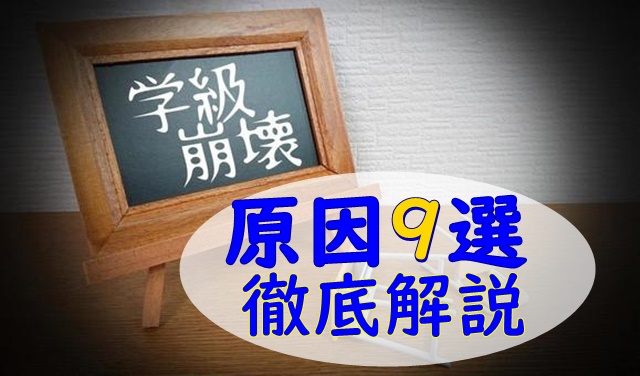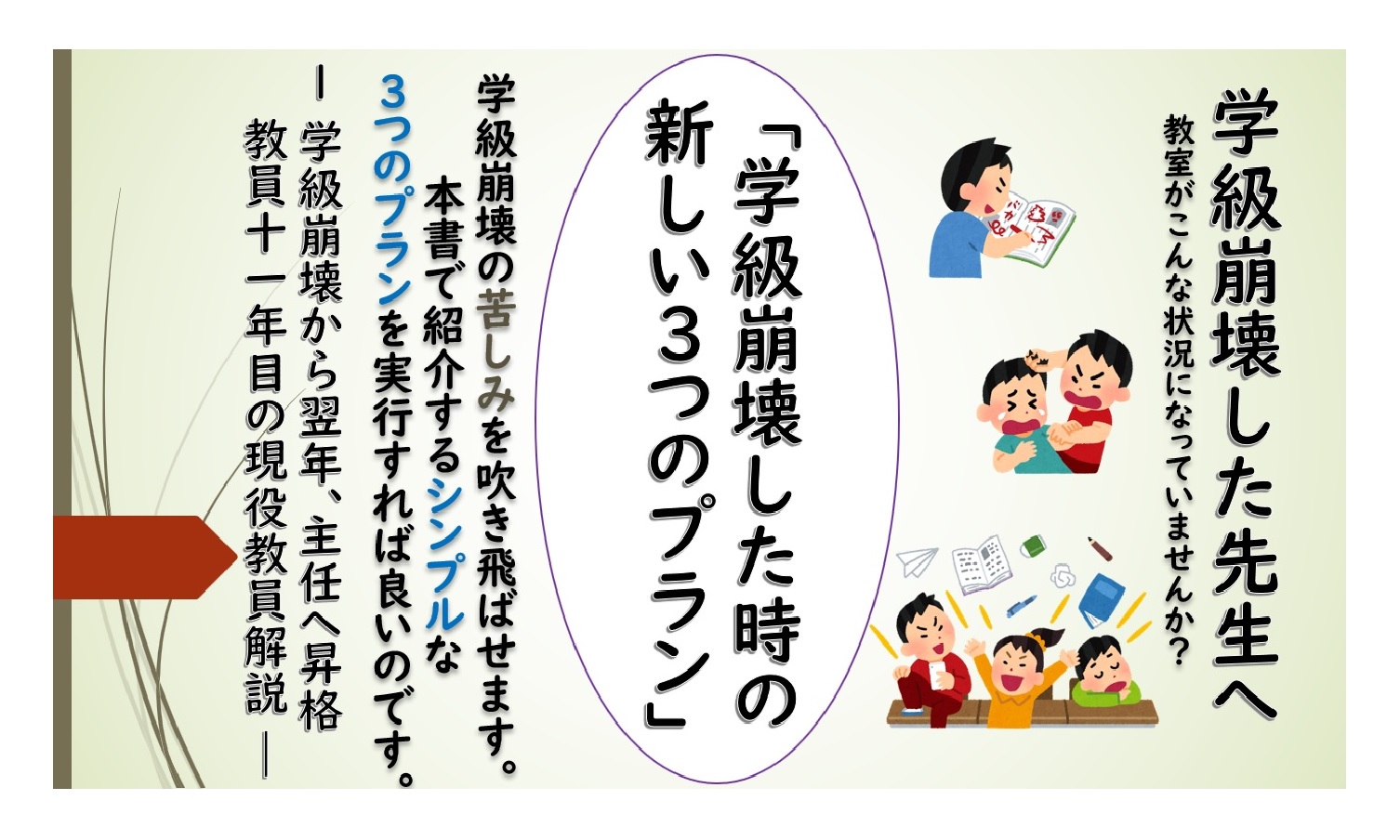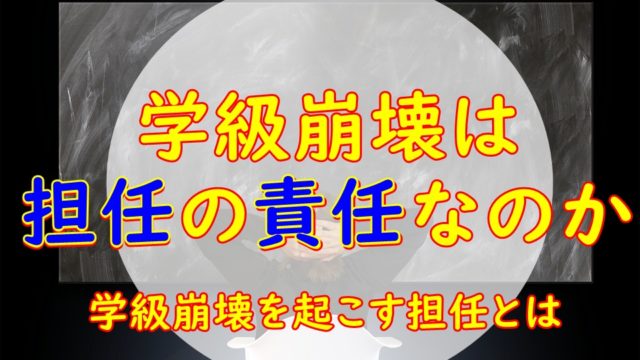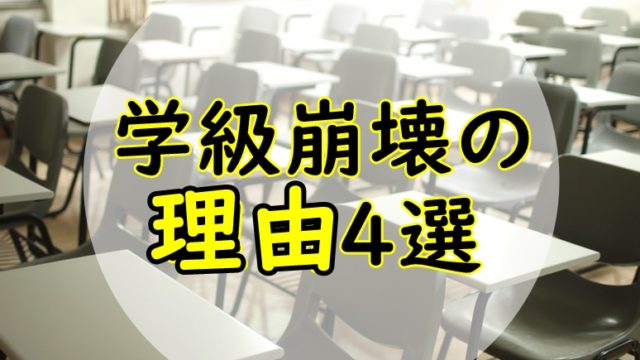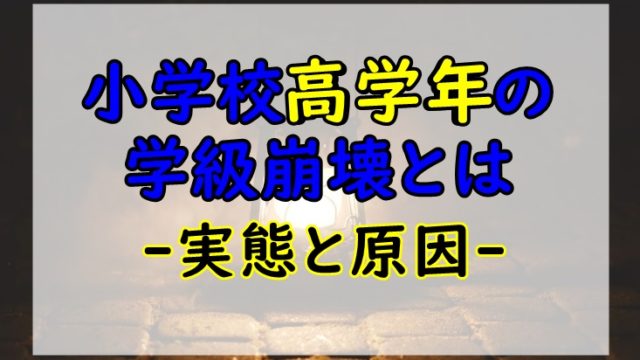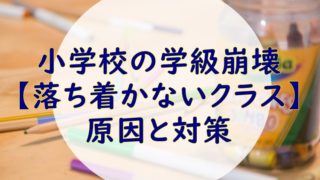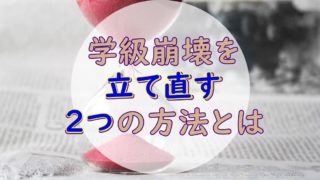学級崩壊の原因を完全に特定するのは難しいとされています。
しかし、学級に起きている現状を整理していくことで、ある程度の原因は突き止めることができます。
教員経験10年以上で、現在も現役教員をしています。
これまでの勤務校では、何度も学級崩壊を目撃し、僕自身も過去に学級崩壊した経験があります。
この記事では、こんな疑問に答えます。
学級崩壊の原因は複数の問題がいくつも絡んでいることが多く、一言で「これが原因!」といえることは少ないのです。
しかし、この記事には、学級崩壊の考えられる原因と状況が記載されているので、
学級崩壊の原因を特定するヒントになると思います。
「うちのクラスの学級崩壊の原因はなに?」と悩まれる方は、ぜひ最後までお読みください。
学級崩壊【原因の9選】を解説

学級崩壊の原因として考えられるのは、次の9つです。
- 【先生】が原因
- 【子ども】が原因
- 【親】が原因
- 【地域】が原因
- 【職場の先生】が原因
- 【管理職】が原因
- 【塾や習い事】が原因
- 【学校のシステム】が原因
- 【テレビや動画】が原因
この中のいくつかの原因が絡んで、学級崩壊が起こります。
一度、学級崩壊が起きると、いろんな問題が発生し、学級崩壊の状態が長く続けば続くほど、原因の特定は難しくなります。
学級崩壊の原因について、さらに詳しく解説していきますね。
①学級崩壊【先生】が原因の場合
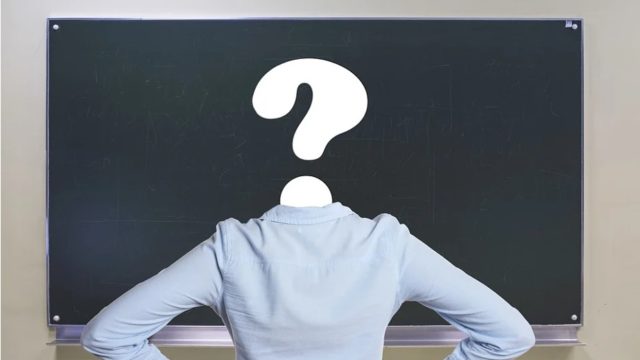
先生が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
教室では学級担任が唯一の大人です。
子どもたちの様子は、大人である担任の先生の影響によって大きく変わることがあります。
先生が原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 先生がいつもイライラしている
- 先生が怖い顔をよくしている
- 先生が子どものことを信頼していない
- 先生のミスやちょっとした間違いがよくある
- テストの採点や課題の返却が遅い
学級担任が子どもたちから責められるようになると、学級は崩壊します。
②学級崩壊【子ども】が原因の場合

子どもが原因で学級崩壊が起きる場合があります。
集団行動を苦手とする子や個性が強い子は、先生の指導についていけなかったり、指導方針に合わなかったりすることが多いです。
教室には、発達障害や子どもが愛着を感じにくい環境に育ったことなど、複雑な事情をもつ子もいます。
そういった個性の強い子が教室の荒れの原因をつくることがあります。
子どもが原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 大人の話を一度で理解できない
- 集団行動が苦手で、気になることがあると集中が切れてしまう
- 嫌なことがあるとカッとなりやすい
- 忘れ物や不注意なミスが多い
- 感情の起伏にムラがある
個性の強い子に対して、教員がしっかりと信頼関係を築き、指導することができれば、学級の荒れを防ぐことができます。
しかし、クラスの子が個性の強い子に流されてしまったり、大人よりも友達を大切にして、先生に反発をしてしまったりすると、学級の荒れが崩壊へとつながります。
③学級崩壊【親】が原因の場合

親が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
親の価値観によって、教育への関心の高さに違いがあります。
- <親の価値観>学校の指導にはきちんと従うべき⇒子どもへの指導が積極的になる
- <親の価値観>学校の指導には従わなくてもよい⇒基本的には学校の指導に合わせるが、子どもが納得していないと親がクレームを入れることがある
- <親の価値観>学校で問題が起こるのは、先生たちの指導力不足⇒学校に起きている問題は学校に任せる。我が子が家できちんとしていれば問題なしと考える
親が「あの先生はよくない」といったことを思っていると、親が気持ちを隠していても、子どもは親に敏感なので伝わってしまうことがあります。
もちろん、納得のできない指導をする先生にも改善が必要なところはあると思いますが、親が教師に不満をもっていると、親子で一緒になって教師へ反発することがあります。
このように、親の不信感が子どもに伝わり、子どもが教師に不信感をもつようになり、学級崩壊につながることもよくあります。
親が原因の場合、次のような状態がよく見られます。
- 「先生はそう言うけど、私の親はやらなくていいって言ってた」と子どもが言うように、学校でのことであっても子どもは親の言うことを聞こうとする
- 先生が「今日はお子さんにこういった指導をしました」と保護者に伝えると、保護者が教師への指導に反発をする
- 保護者は子どもの言うことをすべて鵜呑みにする
- 保護者が授業参観以外の日も頻繁に授業を参観する
- 教室で「先生には従わなくていいってうちの親が言っていた」と子どもが口にする
子どもの中には、学校で何か不満なことがあったときに親に伝えさえすれば、親が先生にクレームを入れてくれると勘違いをしている子もいます。
先生がきちんと保護者に対応をして、保護者が納得できれば学級の荒れは防ぐことができます。
しかし、保護者の価値観が多様化して、先生の指導に納得ができないと、保護者が先生や学校に反発したり、背を向けて協力しないようにすることもあります。
④学級崩壊【地域】が原因の場合

地域が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
学校に批判的な地域、もしくは学校に無関心で非協力的な地域など、地域によって違いがあります。
- 学校に批判的な地域⇒教員よりも年収や地位が高い地域では、教員に対して批判的な見方をすることがある
- 学校に無関心な地域⇒保護者が忙しく、教育に関わる時間があまりない。学校で問題が起きても無関心であることがある。
地域の雰囲気によって学校の子どもたちの様子が変わることがあります。
「先生に叱られてもなんとも思わない。スポーツ少年団の監督の方が怒ると怖いから」と子どもが口にすることがあります。
このように、野球やサッカーなどの地域のクラブチームでの大人と子どもの関わり方が学級に影響することもあります。
地域が原因の場合、次のような状態がよく見られます。
- 教員が子どもに指導をした内容を保護者に連絡しても、どの保護者も多忙で真剣に向き合ってくれない
- 学校や教員に対して、保護者が集団でクレームを入れる
- 地域のクラブチームの指導者が子どもたちの中で絶対的な存在となっていて、先生の指導を聞こうとしない
世の中で核家族化が進んでも、実際は、子どもたちは地域の大人の考えに触れて育っています。
地域が勉強に関心がないところだと子どもたちも勉強に関心が向かなく、地域が批判的なところだと子どもたちは教員や学校に批判的になる傾向があります。
⑤学級崩壊【職場の先生】が原因の場合
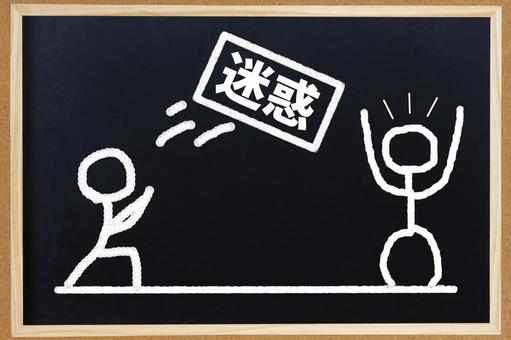
職場の先生が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
学校現場では、先生によって指導の基準がぶれることはよくあります。
例えば、「廊下を移動するときは静かに移動しなさい」と日頃から担任の先生が指導をしていても、担任がいないときに代わりに入った先生が「学校内だから多少は騒がしくてもいい」という指導をすると、子どもたちの規律が乱れます。
担任の先生が許していないことを職場の先生が許してしまうと、子どもたちは都合が良い方を選ぶので、担任の指導を聞こうとしないことが起こります。
職場の先生が原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 子どもたちが授業をする先生によって態度を変える
- 規律の緩い「○○先生がいい!」としきりに口にするようにする
- 担任が出張などでいない時に、子どものトラブルが多発する
職場の先生が学級の子どもたちに甘えさせると、学級の先生が後から苦労をするようになります。
担任の先生が規律を守るように厳しく指導しても、「○○先生はやっていいって言ってた!」というように、学級担任が子どもたちから責められるようになると、学級は崩壊します。
⑥学級崩壊【管理職】が原因の場合

校長や教頭が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
校長や教頭は学校で大きな権限を持っています。
とくに、若い先生ほど管理職の意見に従う機会が多く、学級が崩れたときに管理職が意見を言ったり、担任の代わりに保護者の対応をしたりすることがあります。
大きな権限をもっているからこそ、管理職が判断を誤ると学級にも大きな影響が出ます。
管理職が原因の場合、教室や学校では次のような状態がよく見られます。
- 学級担任の困り感を管理職が理解しておらず、学級が苦しい状態でも担任が一人で頑張っている
- 担任が一人だけでは対応できないことでも、管理職が担任に丸投げをする
- 担任の知らないところで保護者の学校への不満が高まっている
管理職は学校全体を見ているため、細かいところや正確な事実を見誤って判断を間違えることがあります。
学級担任の思いと管理職の思い、子どもたちの思いがバラバラになると学級は崩壊します。
管理職の判断ミスによって学級が荒れることも十分あり得ます。
⑦学級崩壊【塾や習い事】が原因の場合

子どもが通う塾や習い事が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
地域によっては、学校を批判して子どもを塾や習い事教室に募集するところがあります。
「○○学校の指導に従っていたら力はつきません」といったようなことを言う塾の先生もいます。
また、習いごとに体力を奪われ、学校生活に活力がない子どももいます。
塾や習い事が原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 授業中に「塾で習ったから勉強しなくてもいい」と子どもが言う
- 「習い事の先生から学校の勉強は後回しでいいと言われた」と子どもが言う
- 習いごとに疲れ切って、子どもが授業中に居眠りをする
- 塾や習い事教室の先生の姿を見て、子どもが学校の先生をバカにする
もちろん、きちんとした塾や習い事教室がほとんどですが、場所によっては学校批判が強いところもあります。
子どもたちは大人の言うことに敏感なので、塾や習い事の先生が言うことを真似して、
学級担任を責めるようになると、学級は崩壊します。
⑧学級崩壊【学校のシステム】が原因の場合
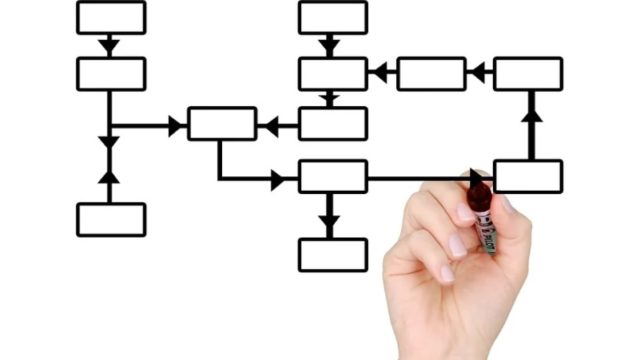
学校のシステムが原因で学級崩壊が起きる場合があります。
教員が不足しており、担任の先生が体調不良のように突然の欠勤があった場合、代わりの先生が見つからないということがある。
そのため、担任の先生がいないと授業が自習になったり、子どもたちが乱れても誰も止める人がいないなど、規律が保てなくなることがあります。
学校のシステムが原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 担任の先生が休むと、授業が自習になる
- 授業は代わりの先生が入るが、清掃の時間や休憩の時間は先生の目が届かない
- 担任の先生がしばらく休むと、学級が乱れる
学校現場では、学級担任が休むと代わりの先生がすぐに入ることができないのが現状です。
先生の目が行き届かなくなると、子どもたちは規律を守る意識が薄れていき、学級が崩壊します。
⑨学級崩壊【テレビや動画】が原因の場合

テレビや動画が原因で学級崩壊が起きる場合があります。
メインの原因とは言いにくいですが、テレビや動画が学級崩壊の一因となることがあります。
子どもの言葉はテレビやYouTubeなどの影響を強く受けます。
テレビや動画が原因の場合、教室では次のような状態がよく見られます。
- 「ぶっこ〇す!」や「うっせぇわ」など汚い言葉が飛び交う
- 汚い言葉が出ても周りの子どもがウケてしまう
- 先生を流行りの言葉で非難する
子どもたちは、意味を十分に理解せずに、人を傷つける言葉を使ったり、汚い言葉遣いをしたりします。
言葉遣いが荒れると、学級の荒れにもつながります。
学級崩壊の原因が分かった後の行動

学級崩壊が起きると、子どもたちの甘えが一気に加速します。
そのため、子どもたちの「やりたくない」「やらない」の理由を一つずつ確実に潰していきましょう。
学級崩壊で先生がとるべき対応
学級崩壊が起きたら担任1人の力だけで回復するのは不可能です。
職場のいろんな人に力を借りましょう。
- 管理職の力を借りる
- 生徒指導の先生の力を借りる
- 前年度担任の力を借りる
- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの力を借りる
- 先輩先生の力を借りる
学級崩壊が起きた時に担任が取るべき行動は「力がないのなら力を借りろ」。
学校現場でできる力を借りる方法はこちら。
- 管理職に報告、相談。保護者対応にも応じてもらう。
- 生徒指導の先生より助言もしくは子どもに直接指導をしてもらう
- 前年度担任から子どもの特性を洗い出す
- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーから子どものあつかい方を学ぶ
- 先輩先生から学級経営や生徒指導、授業について学ぶ
学級崩壊が起きた時は、「まずはやれるだけのことはやる」という気持ちで行動に移しましょう。
学級崩壊が起きた時にとるべき行動について、さらに詳しく知りたい方はこちら(有料)をご覧ください。
学級崩壊で保護者がとるべき対応
学級崩壊が起きたら、まずは落ち着いて学校を信じましょう。
保護者ができる行動はこちら。
- 子どもの話をよく聞くが、すべてだとは信じ込まない
- 心配な点があれば担任に連絡し確認する
- それでも心配な場合は管理職に相談する
子どもの話だけでは事実が見えてきません。
学校で学級をいちばん客観的に見ているのは管理職です。
子どもや担任の話だけでは納得できない場合は、保護者は管理職に相談しましょう。
保護者として自分の目で確かめて見るのもいいと思います。
学級崩壊の原因まとめ

- 複数に絡んでいる場合が多い
- 冷静な対応を心がけるべき
- 問題を一つずつ潰していくことがベスト
学級崩壊の原因は、学級の子どもたちの様子をよく観察することで見えてきます。
学校崩壊の解決は、原因を担任のせいや保護者のせいと決めつけず、原因を一つずつ潰していくしか方法はありません。
そのためには、教員も保護者も協力する姿勢が大切です。
保護者も助けるつもりで学校に積極的に協力しましょう。
学級崩壊が起きた時は、問題が絡み合い、何が悪いのかよく分からない状態となります。
問題を整理するためにも、学級崩壊が起きた時には、この記事を繰り返しお読みください。
この記事を読んで、原因を特定できれば、学級崩壊の改善に繋がます。
そうすれば、今のクラスを子どもたちにとって少しずつ居心地の良いクラスにすることができます。